2023年~2024年にかけて、大人気小説「薬屋のひとりごと」がアニメ化されています。中華系ファンタジー作品では普段耳慣れない単語が多く出てくるので、アニメや小説を読んでもなかなかぱっと理解するのが難しいことがあるのではないでしょうか。
本日は、「薬屋のひとりごと」をはじめとした中華系作品に頻出する用語を簡単に説明していきます。
※今回はわかりやすさ重視、かつファンタジー小説に寄せた記述です。本格的な歴史理解・用語の定義のニュアンスが表現しきれていない場合があります。
皇帝関連の用語
帝(みかど)
帝は君主や皇帝のこと。「王様(King)」と「皇帝(Emperor)」の違いになると話が難しくなってきますが、実は現代において「キング」より格上の「エンペラー」と呼ばれるのは日本の天皇陛下だけだそうです。
東宮(とうぐう)
東宮は帝の息子が住む場所です。転じて、東宮、東宮様といった形で皇太子そのものを呼称するケースもあります。
下賜(かし)
「薬屋のひとりごと」で出てきた用語でわからなかったものNo1はこちら、「下賜(かし)」ではないでしょうか。「下賜する」とは、身分の高い人、特に皇帝や天皇などが臣下に対してものを与えることです。下げ渡すものはモノであったり、土地であったり、はたまた妃であることもあります。皇帝が自分の部下に対して何かの褒美に「妃を下賜する」というケースがあるということです。
似た言葉に「恩賜(おんし)」があります。こちらは目線がもらう側となり、皇帝・天皇からものをいただくことを意味します。なので聞いたことがある「上野恩賜公園」「井の頭恩賜公園」などは、天皇からいただいた公園ですよ~ということですね。意外と現代でも残ってます。
寵愛(ちょうあい)
帝が特定の人物に愛情を示すこと。後宮では寵愛を受けるかどうかが妃にとっては一大事です。
寵妃(ちょうひ)
帝から特に寵愛されている妃。
後宮関連の用語・妃の位
後宮にはたくさんの妃が住んでいることが多いですが、それぞれ位で言うと以下になります。
(時代によって微妙に違うのですが、唐あたりを参考にしています)
| 皇后 | 皇帝の正妻 |
|---|---|
| 四夫人 | 貴妃、淑妃、徳妃、賢妃(正一品) |
| 九嬪 | 昭儀、昭容、昭媛、修儀、修容、修媛、充儀、充容、充媛(正二品) |
| 二十七世婦 | 婕妤九人(正三品) 美人九人(正四品) 才人九人(正五品) |
| 八十一御妻 | 宝林二十七人(正六品) 御女二十七人(正七品) 采女二十七人(正八品) |
| 侍女 | 妃の世話などを行う身分のある仕事。 |
| 下女 | 洗濯・掃除・炊事などを行う。雑用係。 |
それでは、それぞれの説明を見ていきましょう。
後宮(こうきゅう)
後宮は皇帝や王などの妃や側室の女性たちが住む場所を指します。中国だけかと思いきや日本にもあり、有名な「大奥」もいわゆる後宮です。国や時代により差はあれど多くは男子禁制の場で、皇后や妃の生活を支えるための女官や宦官が配置されました。
ここからはドラマや小説でよく出てくる妃の位について。基本となっていそうな唐王朝自体を参考にしていきます。
皇后(こうごう)
皇帝の正室(せいしつ)、つまり本妻。すべての側室や侍女をとりまとめる後宮という組織のトップ。
四夫人(よんふじん)
皇后の次に来るのが、四夫人。四妃とも。
貴妃(きひ)、淑妃(しゅくひ)、徳妃(とくひ)、賢妃(けんぴ)の4つの役職に、一人ずつ妃が任命されます。貴妃から順番に身分が高いです。
漢字が多くて難しくなってきましたが、わたしたちはすでに有名な貴妃を知っています。
そう、世界三大美女「楊貴妃(ようきひ)」です。これ実は楊が姓なんです。貴妃の楊さん。
宦官(かんがん)
去勢された男性の役人。後宮にいる女性はすべて皇帝のものなので、間違いがないよう宦官が役人として使役されていたようです。深く調べると怖いです。。
女官(にょかん)官女(かんにょ)
女性の文官。「薬屋のひとりごと」では試験に受からないとなれない。後宮で働く場合は女官と呼ばれることが多い。ひな人形でも三人官女いますよね。
侍女(じじょ)
高貴な女性の世話などをする身分のある仕事。いわゆるメイド。「薬屋のひとりごと」で言うとそれぞれの妃の周りにいる、妃の色の服をまとった人たち。
下女(げじょ)
洗濯・掃除・炊事などを行う。雑用係。
入内(じゅだい)
妃として後宮にあがること。「後宮に入内する」
花街関連の用語
花街(はなまち)
芸者屋、遊女屋が集まっている地域。歓楽街。
妓楼(ぎろう)
妓女がいるお店。
妓女(ぎじょ)
踊りや楽器などの芸をしたり、男性の相手をする仕事の女性。
身請け(みうけ)
妓女の身代金や前借金を支払い、年季が明ける前に仕事を辞めさせて妓楼から出してあげること
年季(ねんき)
奉公の期限。妓女の場合、売られた金額によって奉公の契約年数が決まっている。
大店(おおだな)
規模の大きなお店
禿(かむろ)
「はげ」だと思ってたらかむろでした。妓楼に住む童女のことを指し、先輩につきながら遊郭のことをいろいろ教えてもらいます。
醜女(しこめ)
容姿が見にくい女性。不細工な女性のこと。
食べ物・薬・毒
山査子(さんざし)
赤い実がつく果実。中国とかでよく食べられる。
冬虫夏草(とうちゅうかそう)
幼虫に寄生したキノコ。漢方や東洋医学で用いられる。
牛黄(ごおう)
牛の胆のう中に生じた胆石。薬の材料になる。非常に貴重で高価。
白粉(おしろい)
化粧用の白い粉。今でいうファンデーション。昔は鉛が入ったものが用いられ、毒となった。
その他_四神
中国の神話上の生き物。様々なモチーフになっているので基礎知識だけ。
青龍(せいりゅう)
神話上の青い竜。方角は東、季節は春、色は緑(青)担当。
朱雀(すざく)
神話上の赤い鳥。方角は南、季節は夏、色は赤担当。
白虎(びゃっこ)
神話上の白い虎。方角は西、季節は秋、色は白担当。
玄武(げんぶ)
神話上の黒い亀。方角は北、季節は冬、色は黒担当。

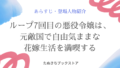
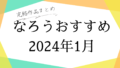
コメント